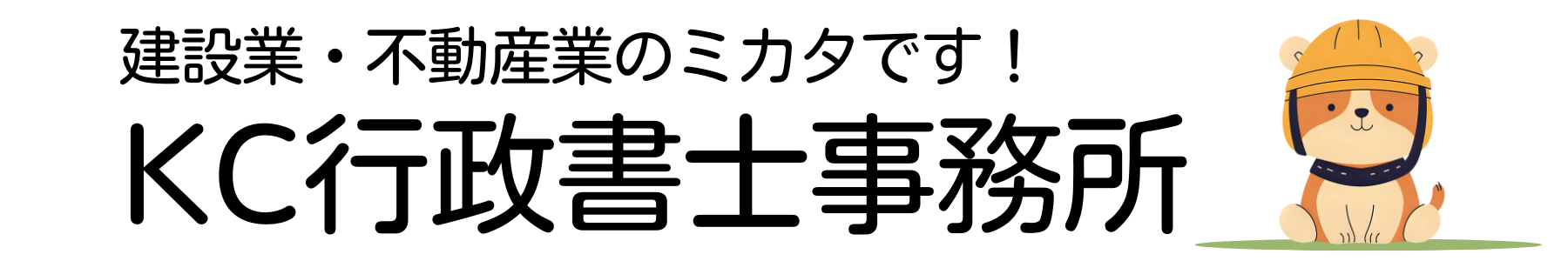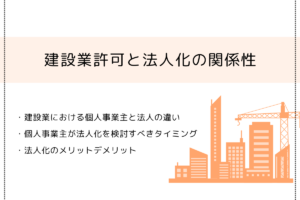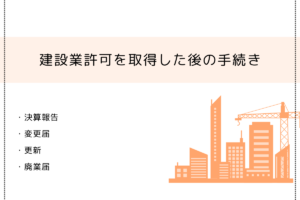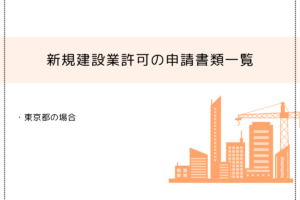建設業許可の申請では建設業法に定める許可の基準に基づいて審査されます。この基準を満たさなければ許可は受けられませんので、申請において最も重要なポイントとなります。
建設業法ではこの許可基準について、4つの項目で定められています。
- 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること
- 営業所ごとに、営業所技術者を専任の者として置く者であること
- 不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと
- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎を有すること
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
【1】建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること
建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が最低でも1人は必要とされます。建設業は他の産業とは異なり特殊なため、一定の経験値が重要視されるのです。
具体的には、以下の①②のいずれかを満たす必要があります。
①法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合本人または支配人のうちの1人が、次の(1)~(3)の3つのうちいずれかに該当する
②法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合本人または支配人のうちの1人が、次の(4)~(5)の2つのうちいずれかの経験を有する者
かつ
常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く
→一人が複数の経験を兼ねることは可能
※当該要件に該当するか否かは、個別ケースごとに審査が行われるため、管轄行政庁への確認が必要です。
さらに、適正な社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)への加入も必要です。
【2】営業所ごとに専任技術者を置くこと
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するため、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(営業所技術者等)を専任で設置することが必要です。
この営業所技術者に求められる資格が、一般建設業か特定建設業か、取得する建設業の種類によって異なります。

一般建設業
以下の3つの要件のうち、いずれかを満たす必要があります。
特定建設業
基本的に以下の2つのうち、いずれかを満たす必要があります。ただし、指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)の許可を受けようとする場合は、施工技術の総合性が考慮されるため、国家資格が必須となっています。
専任技術者の専任性について
「専任」の者とはその営業所に常勤して、専らその職務に従事する者のことをいいます。よって、
同一法人であっても他の営業所の専任技術者を兼ねることはできません。
経営業務の管理責任者と専任技術者を兼務することは可能です。
【3】誠実性
請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。
具体的には、請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為や、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等請負契約に違反する行為などです。
なお、建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者は、原則として不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者として取り扱います。
【4】財産的基礎等
建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入等、一定の準備資金が必要になるため、財産的基礎を有していること等を要件としています。
要件は一般建設業と特定建設業で異なります。
一般建設業
次の3つのうちいずれかを満たす必要があります。
- 自己資本が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力を有すること
- 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
特定建設業
次のすべてに該当することが必要です。
- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上であること
- 自己資本の額が4,000万円以上であること
欠格要件
許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合は許可は行われません。
また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が建設業法に定める欠格要件に1つでも該当すると許可は受けられません。以下の14の欠格要件が規定されています。
①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
②一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
③一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る聴聞通知を受け取った後、廃業の届出をした場合に届出から5年を経過しないもの
④聴聞通知を受け取った日から取消処分がされた日(取消処分をしないことの決定がされた日)までの間に廃業の届出をした場合、聴聞通知を受け取った日から遡って60日前までの間に当該廃業届出をした法人の役員等若しくは政令使用人であった者(個人事業主の政令使用人を含む。)で、廃業届出の日から5年を経過しないもの
⑤建設業法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
⑥建設業法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
⑦禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑧建設業法等に違反したこと又は刑法の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑨暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑩心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
⑪未成年者の法定代理人が建設業法第8条各号のいずれかに該当するもの
⑫法人の役員等又は政令で定める使用人のうちに、建設業法第8条第1号から第4号まで又は第6号から第10号までのいずれかに該当する者のあるもの
⑬個人で政令で定める使用人のうちに、建設業法第8条第1号から第4号まで又は第6号から第10号までのいずれかに該当する者のあるもの
⑭暴力団員等がその事業活動を支配する者