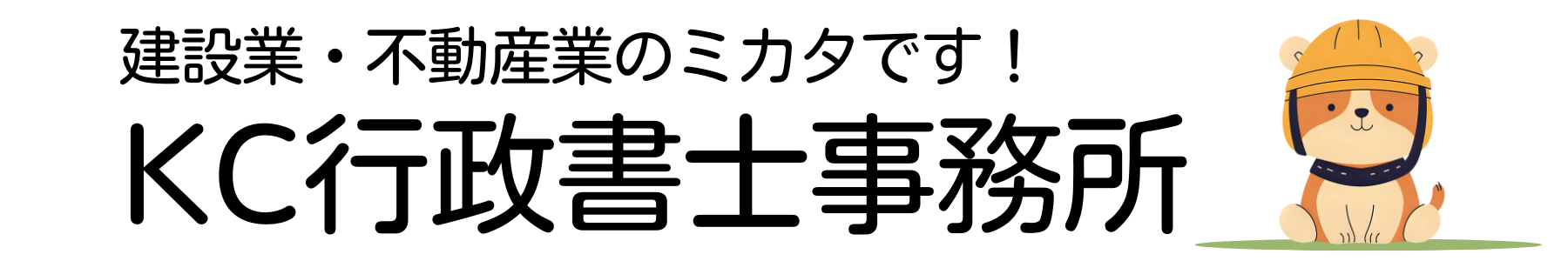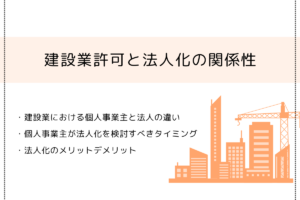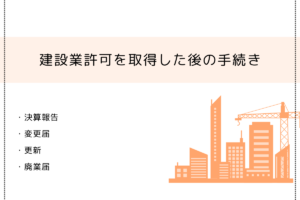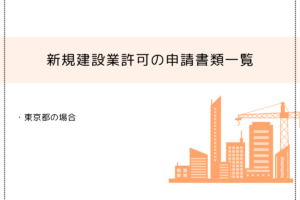建設業を営む際に必要になる許認可が建設業許可です。
といっても、具体的にどの範囲の工事業が許可が必要となる「建設業」に該当するのかわからないという方もいるのではないでしょうか。
また、建設業法では「軽微な建設工事のみを請け負う」場合には建設業許可は不要であるとされています。この軽微な建設工事の範囲についても気になりますよね。
当ページでは、そんな「建設業許可が実際に必要になるケース」を説明いたします。
建設業とは?
建設業とは建設業法で定義されており、具体的には以下のような工事を請け負う営業を指します。
・土木一式工事
・建築一式工事
・大工工事
・左官工事
・とび・土工・コンクリート工事
・石工事
・屋根工事
・電気工事
・管工事
・タイル・れんが・ブロツク工事
・鋼構造物工事
・鉄筋工事
・舗装工事
・しゆんせつ工事
・板金工事
・ガラス工事
・塗装工事
・防水工事
・内装仕上工事
・機械器具設置工事
・熱絶縁工事
・電気通信工事
・造園工事
・さく井工事
・建具工事
・水道施設工事
・消防施設工事
・清掃施設工事
・解体工事
このように建設業に定義される工事は細かく区分されているわけですが、大きく「土木一式工事・建築一式工事」の2つの一式工事と、それ以外の専門工事に分けられます。一式工事とは、土木工作物や建築物を総合的に管理統括する、いわゆる「元請け」の立場を指します。
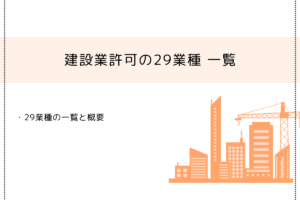
軽微な建設工事とは?
では次に、上記のような建設業を営む会社であっても例外的に建設業許可の取得が不要とされる「軽微な建設工事」を見ていきましょう。
「軽微」の考え方として、基本的には工事1件当たりの請負金額で判断します。具体的には以下です。
| 建築一式工事 | 1,500万円(税込)に満たない工事 |
| または | |
| 延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事 | |
| それ以外の工事 | 500万円(税込)に満たない工事 |
この金額の算定には、以下の4点に注意しなければなりません。
①2つ以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負金額の合計額
つまり、600万円の電気工事を300万円×2回分の契約にわけても、軽微な建設工事には該当しないよ、ということですね。
②注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含む額
例えば、お客さんが材木屋さんで木材はうちのを使って、などという場合、取引額はその材料費分安くなるわけですが、請負代金には算入して考えなければならない、ということです。
③単価契約とする場合は、1件の工事に係る全体の額
単価契約とは、全体にかかる数量を工事前に算定することが難しい場合に、単価を定めておいて実際の数量で代金を支払う契約のことですが、この場合は全体の額で考えてくださいね、ということです。
④消費税及び地方消費税を含む額
税込みで考えなければなりませんので、正味としては500万円(1,500万円)よりも少ない額になります。
結論:建設業許可が必要なケース
以上を踏まえ、建設業許可が必要なのはどんな場合なのかをまとめましょう。
- 建築一式工事の場合は、1回の請負代金が1,500万円以上の工事を受注する
- もしくは、延べ面積150㎡以上の工事を受注する
- それ以外の工事の場合は、1回の請負代金が500万円以上の工事を受注する
このように受注する工事が一定規模を上回る場合に建設業許可が必要となります。お客さんからこの規模の工事依頼の可能性がある場合など、今後の事業を見据え、取得すべきか早めに検討しておくとよいでしょう。